興行的にも批評的にも好評な「国宝」はアカデミー賞国際長編映画賞に出品されます。これが受賞なるかどうかは映画好きの私には村上春樹がノーベル賞受賞するかどうか以上に気になります。
そこでアメリカのエンタテイメント雑誌に掲載された「国宝」の批評からアカデミー賞への期待をはかってみましょう。
ここではハリウッド・レポーター誌のシェリー・リンドン氏のレビューを見てみましょう。
映画国宝海外の反応 『国宝』レビュー:日本がアカデミー賞にノミネートした作品は、歌舞伎の世界を舞台に、芸術、野望、そして血統を描いた驚異的な物語
李相日監督の長編映画『国宝』は、舞台裏のメロドラマと継承者の物語が融合し、吉沢亮と横浜流星が主演を務め、渡辺謙が重要な助演を務めます。
『国宝』は、歌舞伎という高尚な世界を描いた近年のフィクション作品から題名と小説的な広がりを拝借し、1960年代半ばに始まり、50年後に幕を閉じる。李相日監督の長編映画は、日本の近代史を深く掘り下げながらも、その背景をあえて説明することなく、オペラ的な緊迫感と視覚的な詩情によって推進されている。
物語は3時間にわたって展開され、その大部分は心を奪われるもので、時折、物語の勢いがギザギザに途切れるのみ。歌舞伎の伝統に生まれた俳優と、その座を駆け上がろうと決意したアウトサイダー、2人の俳優志望者の双子の物語を通して、この映画は舞台裏のメロドラマ、襲名劇、そしてアーティストの成長過程を巧みに織り交ぜている。素晴らしいキャスト陣の中心人物として、吉沢亮と横浜流星が、舞台裏のキャラクター描写と舞台上の演劇性を織り交ぜた、絶妙に重層的な演技を披露している。
犯罪ドラマ『悪人』(2010年)と殺人ミステリー『怒り』(2016年)に続き、『国宝』は李監督による吉田修一原作の3作目の映画化作品となる。アカデミー賞国際長編映画部門への日本からの正式出品作品である本作は、アメリカ映画祭AFIフェストで初上映され、11月中旬から限定公開される。
映画国宝海外の反応 李相日監督と脚本を書いた奥寺佐登子の狙い
奥寺佐登子の脚本に基づき、李は女形に焦点を当てる。女形は、17世紀に将軍が女性の歌舞伎出演を禁じて以来、歌舞伎で女性役を演じてきた男性俳優である。物語の中では、フェミニズム的なものであろうとなかろうと、この伝統を疑問視することはない。あるのは、女形の追求と、その芸術性に対する尊敬の念だけだ。
「国宝」が考察する両刃の剣は、社会通念ではなく、登場人物の軌跡である。題名は国家が指定して特別に保護・管理する建築物や美術品などを意味する。登場人物が女方をこのように表現し、「彼は死んだら芸しか残らないだろう」と述べるとき、それは悲しい言葉として込められている。
しかし、李と奥寺はそれを最高の賛辞として込めている。この映画は、俳優たちの虚栄心――ある登場人物は彼らを「強欲な生き物」と評した――を認めながらも、少なくとも観客に対しては、彼らの努力と、どれほどの自己を捧げているかを称賛している。もちろん、見知らぬ人なら簡単に受け入れられる。
映画国宝海外の反応 主要人物のキャラクターが担うものは何か?
吉沢と横浜が40分ほどで中心的な役割を担うまでは、主人公は黒川蒼也と越山啓達の見事な演技によって10代の若者たちで構成されている。映画は長崎に珍しく降る雪のシーンから始まり、その忘れがたい魅力が映画のモチーフとなり、軽やかながらも効果的に用いられている。ヤクザ(永瀬正敏)が催す新年の宴席で、来場していた歌舞伎役者の名優、花井半次郎(渡辺謙。『怒り』や、李監督による2013年のリメイク版『許されざる者』にも出演)は、亭主の息子で14歳の喜久雄(黒川)の才能に気づく。喜久雄は精力的に、そして献身的に歌舞伎の女形を演じる。
1年後、喜久雄の父が殺害され、喜久雄は(画面外で)父の復讐を試みて失敗した。継母(宮澤エマ)は、喜久雄を犯罪から遠ざけようと、大阪へ送り、丹波屋家として知られる歌舞伎役者の家系を継ぐ花井に弟子入りさせる。花井の妻、幸子(寺島しのぶ)は懐疑的ながらも寛容で、喜久雄を事実上養子として育て、修行を手伝うことに同意する。(喜久雄は、胸が張り裂けるような余談として、実母が「原爆症」で亡くなったことを明かす。)
荒々しく、言葉遣いも侮辱的な彼のやり方は、今日では通用しないだろうし、1965年当時は眉をひそめる者もいた。しかし、注目を浴びて花開き、傷跡など気にも留めない菊夫は、彼を「素晴らしい」師匠とみなしていた。
花井半次郎は喜久雄に花井東一郎という芸名を与え、孤児のヤクザの息子を自身の歌舞伎の系譜に連ねる。幸子は心配そうに見守る。喜久雄が歌舞伎の天性の才能なのか、俊介よりも野心的なだけなのか ― あるいは、後に幸子が言うように「汚い泥棒」なのか ― 師匠は喜久雄の才能だけでなく勇気も認めていた。しかし、その道のりは決して平坦なものではなかった。
喜久雄に警告を発するのは、有名な老女方、万菊(田中泯が魅力的に演じている)で、喜久雄の美貌が芸の邪魔になるかもしれないと告げる。舞台上の万菊の姿を見た喜久雄は、ある啓示を受け、劇中劇の第一幕の幕を閉じます。そして物語は1972年へと移ります。吉沢と横浜が演じる喜久雄と俊介は、共に女形として修行を積んできた若者です。
『藤の乙女』(タイトルカードに簡潔なあらすじが記されています)などの作品では、古典的な化粧と精巧な衣装に身を包み、シンクロナイズドスイマーのように規律正しく均整のとれた動きを見せます。花井の反対を押し切って、丹波屋の企業家(嶋田久作)が彼らを大劇場に招聘し、たちまち二人の女形デュオという斬新さは、ボーイズバンドのアイドル的人気を博しました。
しかし、舞台を降りた二人は、必ずしも息が合った演技をしているわけではありません。俊介は宣伝活動と観客獲得に気を取られているのです。そして、彼は次第に、舞台パートナーのような生まれ持った才能が自分にはないかもしれないと自覚していくのです。
荒々しく、言葉遣いも侮辱的な彼のやり方は、今日では通用しないだろうし、1965年当時は眉をひそめる者もいた。しかし、注目を浴びて花開き、傷跡など気にも留めない喜久雄は、彼を「素晴らしい」師匠とみなしていた。花井半次郎は喜久雄に花井東一郎という芸名を与え、孤児のヤクザの息子を自身の歌舞伎の系譜に連ねる。幸子は心配そうに見守る。喜久雄が歌舞伎の天性の才能なのか、俊介よりも野心的なだけなのか ― あるいは、後に幸子が言うように「汚い泥棒」なのか ― 師匠は喜久雄の才能だけでなく勇気も認めていた。しかし、その道のりは決して平坦なものではなかった。
喜久雄に警告を発するのは、有名な老女方、万菊(田中泯が魅力的に演じている)で、喜久雄の美貌が芸の邪魔になるかもしれないと告げる。舞台上の万菊の姿を見た喜久雄は、ある啓示を受け、劇中劇の第一幕の幕を閉じます。
そして物語は1972年へと移ります。吉沢と横浜が演じる喜久雄と俊介は、共に女形として修行を積んできた若者です。『藤の乙女』(タイトルカードに簡潔なあらすじが記されています)などの作品では、古典的な化粧と精巧な衣装に身を包み、シンクロナイズドスイマーのように規律正しく均整のとれた動きを見せます。
花井の反対を押し切って、丹波屋の企業家(嶋田久作)が彼らを大劇場に招聘し、たちまち二人の女形デュオという斬新さは、ボーイズバンドのアイドル的人気を博しました。
しかし、舞台を降りた二人は、必ずしも息が合った演技をしているわけではありません。俊介は宣伝活動と観客獲得に気を取られているのです。そして、彼は次第に、舞台パートナーのような生まれ持った才能が自分にはないかもしれないと自覚していくのです。
喜久雄の恋人である春江(高畑充希)でさえ、喜久雄の芸術への情熱には到底及ばないことを理解している。観客席でそれぞれ席に座る春江と俊介は、喜久雄が『心中』で主役を演じるのを目の当たりにし、彼にとってカタルシスをもたらし、人生を変えるような出来事を目撃していることを悟る。舞台上の復讐、絶望、そして痛切なセリフ、そして喜久雄の勝利が彼を取り巻く二人の人物にどのような影響を与えるかを描いた舞台裏のシーンは、この映画で最も力強いシーンの一つだ。脚本は力強く(「僕は偽りの俳優ではなく、本物の俳優になりたいんだ」と俊介は涙ながらに告白する)、編集は今井剛が手掛けている。
映画国宝海外の反応 美術とカメラワークの秀逸さ
美術監督の種田陽平(『キル・ビル Vol.1』、『思い出のマーニー』)は、幅広い時代背景における多種多様な生活空間を創造するだけでなく、歌舞伎舞台装置に様式化され、鮮やかに表現された舞台美術も手がけています。同様に、小川久美子の衣裳は、登場人物を特徴づける衣装だけでなく、舞台上での緊迫感のある衣装替えを想定して作られた、精巧な衣装も含まれています。
ソフィアン・エル・ファニ(『アデルは熱い色』)の撮影は、質感と光の戯れを鮮やかに捉え、特に歌舞伎役者のクローズアップは、仮面のような化粧を通して多くのものを露わにする彼らの表情に細心の注意を払っています。
原麻里彦の音楽は、オーケストラのうっとりするような響きと、より抑制された、無駄を削ぎ落とした楽器演奏の間を行き来しながら、物語の高揚した叙情性と調和しています。
数十年という時を経て物語が進むにつれ、時折過熱し、後半の登場人物たちの紆余曲折は、心を掴むというよりはむしろ衝撃的になることもある。しかし、喜久雄と俊介の、そして他の登場人物たちの行く末は、全く予測不可能だ。例えば、最初は喜久雄を軽蔑していた実業家(三浦貴大)が、次第に味方になっていく様は、まさにその好例と言えるだろう。
映画国宝海外の反応 芸の道に生きる主人公の確固たる信念と熱狂的な画面の美しさ
それぞれの登場人物が苦悩、勝利、そして逆境に直面しても、主演の二人は決して揺るぎない。芸者(三上愛)との間に生まれた子供のことをほとんど知らないほど情熱的な男を演じ、後に大物俳優(本作の歌舞伎アドバイザーでもある中村鴈治郎)の娘(森七菜)と、もしかしたら都合の良い恋に落ちるような恋に落ちる吉沢は、皮肉っぽくも媚びへつらうでもなく、はるかに興味深く謎めいた何かを提示している。
喜久雄の師であり俊介の父でもある渡辺は、喜久雄に劣らず欠点を抱えながらも、同様に説得力のあるキャラクターに重厚さを与えている。喜久雄に犯罪の過去よりも芸術を重視するよう促し、歌舞伎を極めることで「甘い復讐」ができると告げる。
ある意味、これは結局のところクライム・サーガ(犯罪物の壮大なドラマ)であり、名誉と忠誠の規範を巡る物語なのかもしれない。そして何よりも、それは熱狂的な美しさの物語なのだ。吉沢と横浜は力強く優雅に女形を演じ、歌舞伎という男の世界において二人の役柄は芸術兄弟であり、女性らしさという非現実的な儀式的な概念を体現している。彼らが演じる役者たちは、ただの人間であるがゆえに、より一層魅力的である。
映画国宝海外の反応 アメリカの反応 ストーリーを追って精密に分析するレビュー
今回は多少長い文章でした。スマホの影響なのか長い文章を読むのに慣れてないと途中で投げ出して、ここの文章を読んでいる人は少ないのかもしれません。お疲れさまでした。このレビューを肯定的に見る人も否定的な人も、映画批評はこれだけの文章を綴ると読み応えがあって満足いただけたと思います。役者の演技や監督やスタッフの仕事に気を配って丁寧に記述して私は面白かったですよ。クライム・サーガという表現にはハッとしました。ああ、そうか、「ゴッドファーザー」みたいなものに例えているんだなという視点が面白かったですね。
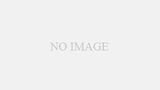

コメント